※本ブログの収益は「サブサハラアフリカ学生への奨学金事業」の準備に使わせていただきます。本ブログの目標は「こちら」から確認いただけます。
こんにちは!仕事を通じて質問力を高めてきた鈴木ケイタです。
皆さんは、質問力を高めたいと思ったことありませんか?「質問力って、学校の授業で先生に質問する力ってこと?」とか、「会社のミーティングで何か質問ありませんか?と聞かれて、いつも質問できていない」とか、いろいろ疑問や悩みを抱えているかと思います。
今日は、質問力って何と感じた人や、質問力を高めたい人向けに、私が仕事を通じて、少しずつ身に着けてきた質問力について説明したいと思います。この記事を読めば、少しずつ質問力を身に着けていくために何が必要なのかについて理解できると思います。

僕は、学校の授業でも質問するのが苦手だよ。
僕も若いうちは、質問するのが苦手だったよ。でも、少しずつ仕事を通じて、質問力を磨いていったんだ。

この記事の信憑性
・筆者は通算400回以上の仕事上の会食経験を有する。
・アポイント先を訪問してのヒアリング経験も豊富。
質問力とは何か
まずは定義を確認
一般的に、「質問力」とは、物事における不明点や疑問点などを問いただす力のことを言います。簡単に言うと、自分で疑問に思ったこと、分からないことを相手に聞く力のことを言います。
質問力の前提には、相手の言ったことを理解しようとする姿勢と、相手への興味が欠かせません。皆さんも、興味のない人に、あれこれと質問しないですよね?それと同じで、質問するということは、相手に対して、ある程度の興味があるってことになります。
質問力が高い人になるためにするべきこと
それでは、その質問力を高めるためにはどうすればいいのか。ここからは、フランス語圏8年間で約400回以上も仕事上の会食を行った経験から、質問力が高い人になるためにするべきことを説明していきたいと思います。
まずは相手のことを知る
まず、質問をするには、ある程度の準備が必要になります。いきなり、相手の話を聞いて、質問することもできなくはないですが、私の経験上、相手のことを調べてから、そのアポイントなり、会食なりに臨んだ方がいいと思います。

具体的に相手の何を調べればいいの?
ケイタ君、質問力の高い質問をしますね(笑)。まず、入手可能ならば、相手の経歴を調べてみましょう。相手がどういうキャリアを歩み、どういう分野の仕事をしていたのかなどについて調べてみましょう。
私は仕事上の会食などで相手に会うときは、必ずインターネットなどで相手の経歴や、相手が出ている記事・ホームページなどを必ずチェックしていました。
また、経歴が分からないときでも、相手が働く組織や、相手の学校のことなら、ある程度インターネットなどで調べることができます。もし最近、その企業などで話題になっていることがあれば、そのことについて調べて予備知識を深めておくいいでしょう。
相手の専門分野について質問する
次に相手の専門分野について質問するようにしましょう。皆さんが質問をするときのことを考えてみれば理解しやすいかと思いますが、質問するときって相手の方が、皆さんより知識が多いことがほとんどではないでしょうか。
その自分が分からない分野が、相手の専門であったりします。専門分野というのは、その人が好きなことであることが多く、自分の好きなことについて聞かれると、とっても嬉しいものです。嬉しいと、ついついたくさん話してしまったり、重要なことをぽろっと話してくれることもあります。

相手の専門分野が分からないときは、どうすればいいの?
相手の専門分野が分かりにくいこともありますが、そのときは、その場でその相手の専門を聞いてみましょう。その専門について、自分の知っていることや興味関心のあることについて話を振ってみて、どんどん相手に答えてもらうようにしましょう。
専門分野に質問するためには、こちらも予習が必要
事前に専門分野が分かったとしとしても、自分がその分野に詳しくなかった場合はどうしたらいいでしょうか。これは、勉強するしかありません。勉強の重要性については、以下の記事でも解説していますが、入門書や概要などを通じて基礎を少しでもかじってから、アポイントや会食などに臨むべきでしょう。
私は国際関係や政治などについてはそこそこ詳しいと自負していますが、法律、科学、医学などについては詳しくはありません。そのため、これらの専門家に会うことになったときは、自分のつたない知識を総動員して、自分の苦手な分野の基礎を理解するようにしていました。
では、専門分野が事前に分からないときは、どうすればいいでしょうか。その時は、もう自分の知識にすがるしかありません。こういうときに真の教養力が求められるのです。私も、レセプションなどで初めて会う人に対して、質問をするときが、まさにこの状況です。
例えば、私は海外でのレセプションなどで積極的にアフリカ人の方によく声をかけました。私が、アフリカの人に興味関心があるから声をかけたのですが、アフリカの人と話すと、母国での日本の支援や、日本の文化の話になることが多いです。
私に話しかけられたアフリカ人は、まさに日本について自分の知っていることを総動員して、私とコミュニケーションをとっているのです。
いい質問をすると、相手も喜ぶ
以上を踏まえて、皆さんが相手に対して、いい質問をしたとします。そうすると、相手は喜んでくれます。なぜなら、まず、あなたが相手に対して興味関心を抱いていることが伝わるからです。
また、授業や講演会などで、皆が疑問に感じていることに対して質問をしたら、先生や講師などはとても助かります。なぜなら、その質問によって、先生なども改めて説明することができますし、その説明によって、生徒などの理解も進むからです。
では、限られた時間内でいい質問をするにはどうすべきか。

結局、いい質問をするためにha
どうしたらいいの?
それは、実践あるのみだね!

ケイタ君のように、「結局いい質問するためにはどうしたらいいの?」という質問に対する答えは、「実践あるのみ」です。
以前、A新聞社の記者の方とお話しする機会があったのですが、私の同僚がその記者に「記者という仕事は、質問力が重要になってくると思いますが、普段からどうやって質問力を高めているんですか?」と質問しました(素晴らしい質問力ですね)。
その記者は、「記者の場合、相手に質問できる時間が少ないことも多い。そのような制約のある中で、「自分ならどんな質問を相手に投げかけるのか。たった1問しか質問できないのならば、自分だったら何について質問するのか」について常に自問自答していくしかない」と回答していました。
要は何度も何度も自問自答して、ベストの質問を考えることが質問力の向上にとって重要ということです。
質問力とは何か。質問力が高い人になるにはどうすべきか。~まとめ~
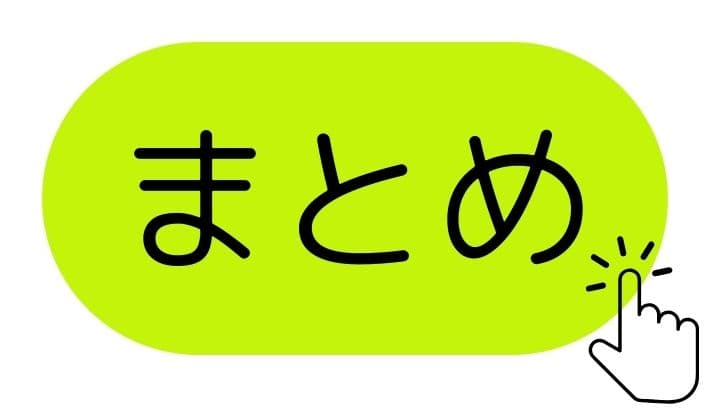
いかがでしたか?最後に今日のおさらいをしておきましょう!
本日のポイント
✅まず、質問相手のことや専門分野を事前に調べて知っておく
✅質問相手の専門分野について質問すると、質問相手は喜ぶ
✅いい質問をするには、実践あるのみ!
✅限られた質問の中でどんな質問をすべきか考える
私も質問するのは苦手でした。でも、以上のことを意識して、400回以上も会食をしていくうちに、少しずつ質問ができるようになってきました。まさに「実践あるのみ」でした。
皆さんも、今日の記事の内容を意識して、質問力を磨いていきましょう!!
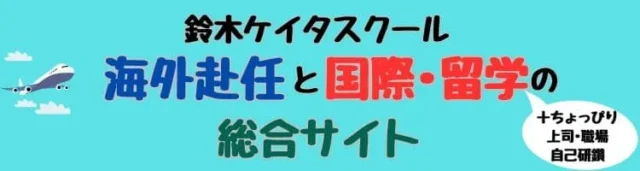





コメント